管理栄養士のmafiです。
[chat face=”kowaiusagi.png” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none”]
- 公務員の管理栄養士を目指している
- 公務員になりたいけれど、管理栄養士の給料はいくらだろう
[/chat]
こんな疑問に答えます。
就職に関して、年収はかなり気になるところ。
- 管理栄養士歴10年
- 市役所の管理栄養士経験者
実際の経験をお話します。
管理栄養士/公務員の年収は高い方

「公務員」といっても、県や病院など様々な職種がありますが、公務員の中でも一番給料が低いのは【市役所】の管理栄養士です。
市役所の場合、大卒で187,200円(2022年4月採用者)からのスタートです。
- 市役所:187,200円から
- 病 院:200,000円から
- 施 設:170,000円から
- 保育所:170,000円から
- 企 業:180,000円から
- (ハローワーク調べ)
こうやって比べると、市役所の管理栄養士は給料が高い方かもしれませんね。
公務員の管理栄養士の年収は最低310万円
年収の計算は、月額の給料と、ボーナス額を足したもの。
給料:187,200円×12カ月=2,246,400円
ボーナス:187,200円×4.4倍=823,680円
合計:3,070,080円
だいたい、310万が年収ですね。
この年収が高いと思う人もいれば、低いと思う人もいるでしょう。
「公務員の多くは「低い」と思っている人が多いと思います。
手当ては人それぞれ
公務員の給料をネットで見ると、400万円程度あると書かれたサイトもありますが、これは「手当て」が入っているためです。
- 残業手当:1時間当たり1,700円程度
- 住居手当:ひと月当たり2万円程度
- 不要手当て:ひと月当たり3~10万円、、、など
1月当たりの手当てが10万円以上付くと、年収も120万円増えてきます。ネットの計算どうりですね。
ちなみに公務員のメリットは30代に入ってから本番
さて、給料が安い安いと言われる公務員ですが、30代に入ると現状は変わります。
30代管理栄養士の年収
- 公務員:年収450万円
- 病 院:年収400万円
- 施 設:年収380万円
- 保育所:年収350万円
- 企 業:年収400万円
40代管理栄養士の年収
- 公務員:年収550万円
- 病 院:年収450万円
- 施 設:年収400万円
- 保育所:年収400万円
- 企 業:年収450万円
50代管理栄養士の年収
- 公務員:年収600万円
- 病 院:年収480万円
- 施 設:年収430万円
- 保育所:年収430万円
- 企 業:年収500万円
なぜこんな差が生まれるのか
ご覧の通り、公務員の年収は順調に上がりますが、病院や施設の年収はほぼほぼ変わりません。
- 公務員の給与は男女変わりがない
- 病院、施設、保育は国の補助金や委託料が収入源なので給与設定が低い
子どもを産んでも産休、育休が保証されているし、コロナ禍でも「やめろ」なんて言われない。
それが公務員ですよね。
公務員の管理栄養士の仕事とは?
そもそも、公務員の管理栄養士はどんな仕事をしてこの給料額なのかというと、
- 多職種間のコーディネート
- 献立作成、栄養指導、助言、教育、実演
- 行政文章やマニュアルの作成
- 広報誌の作成
- 支払いや資料作成などの事務仕事
更に詳しい仕事内容は、コチラの記事に書かいていますので参考に。

公務員の管理栄養士になるメリット
公務員の管理栄養士になるメリットは以下です。
- 休みが取りやすい
- 福利厚生が整っている
- 年齢を重ねても働くことができる
- 指導されるより、”一般の管理栄養士・栄養士を指導する立場”
- 様々な業務を広く浅く経験を積むことができる
将来の年収だけじゃないです。僕もですが、同じ職場や同じ人間関係に飽きやすいタイプなので、定期的な異動のある公務員の職場は過ごしやすかったです。
管理栄養士の公務員向け基礎勉強オススメ参考書5選
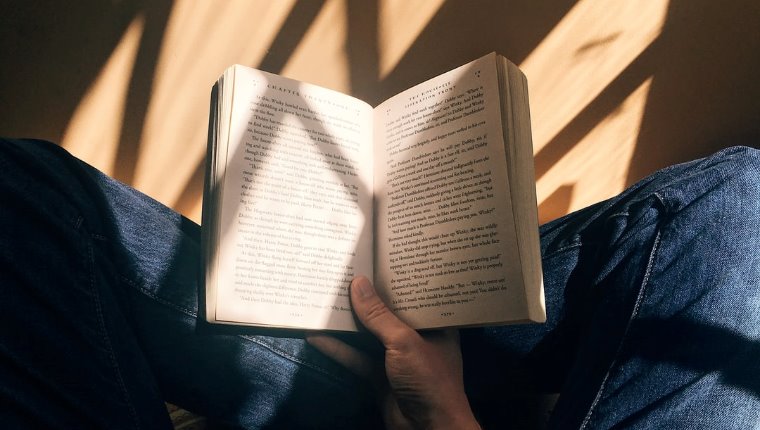
そこで管理栄養士の勉強をしつつ公務員試験の勉強もする、そんな人に向けて、基礎勉強に使うことができる参考書をまとめてみます。
実際に僕も使ってきた本なので、参考書選びに悩んでいたら参考にしてください。
公務員試験 速攻の時事
誰にオススメか
- 公務員試験の勉強をしたことが無い人
- 試験目前で、とりあえず勉強しておきたい人
知る人ぞ知る、有名書籍なので読んでいて損はないはずです。
大学の公務員講座などを受けるつもりが無いのであれば、必ず押さえておきたい本ですよね。
公務員試験マル秘裏ワザ大全
誰にオススメか
- 身近に公務員の親族がいない人
- 公務員的な概念を知らない人
公務員の概念を学ぶのであれば、この本は欠かせません。僕はこの本を読んでいたおかげで、試験勉強をしていない科目も『概念』としての解き方で解くことができたと思っています。
この本を隅々まで読んだ後には、
・韓国
・中国
・アメリカ
・イスラエル
例え問題文がなくても、この選択肢の中から公務員の採用試験に一番最適な選択肢を選ぶことができるようになりますよ。
読んでいる人と読んでいない人では、かなり差が出ます。
公務員試験 受験ジャーナル
誰にオススメか
- 市役所を受験したい人
- 最新の試験問題が知りたい人
意外に知られていないのが、管理栄養士の試験は【中~上級レベル】だということ。
「栄養士」は下~中級レベルです
試験レベルは高いですが、この本さえ押さえておけばOKです。
さらに詳しい勉強方法&小論文系の参考書はコチラの記事でも紹介してます。
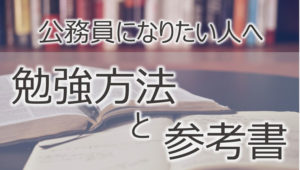
国家公務員と地方公務員の違いとは

公務員を目指している人の中には、「国家公務員」を目指している人もいると思うので参考に。
国家公務員の管理栄養士
- 国の上級試験や、厚労省の管理栄養士枠を受験する
- 給料は○○からスタート
- 全国規模で異動があり、初めから管理職候補が前提
- 30代~50代の社会人経験者が9割
警察学校の管理栄養士、自衛隊の管理栄養士もここに入りますね。
地方公務員
- 県や市の下級から上級の管理栄養士採用枠を受験する
- 給料は、187,200円からスタート
- 県内、市内で異動があり、管理職になれるのは退職間際
- 県・市によって、新採用者、経験者を選んで採用している
県庁、市役所に勤めたい人は地方公務員の採用試験を受けるようになりますね。
地方公務員の基本給を上げる方法とは?
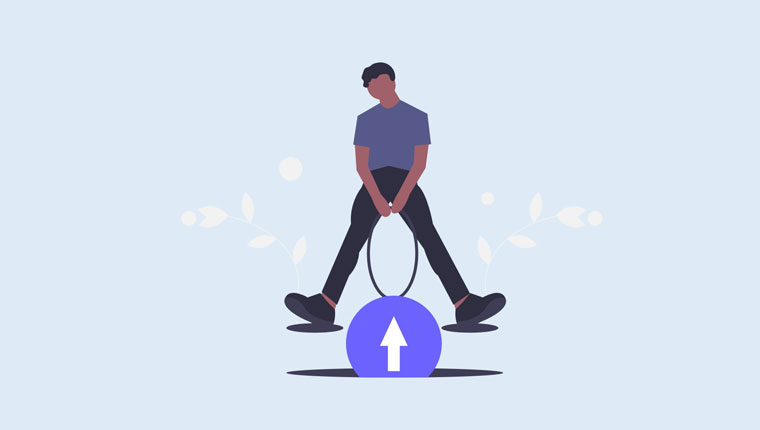
今回例に出している187,200万円は、大卒の新採用職員の基本給になります。
この基本給を上げるには、
- 院卒の学歴
- 社会人経験者
- 基本給の高い政令指定都市や都内の公務員に応募する
などの方法があります。
管理栄養士は栄養士資格と国家試験が必要なので、「高卒」の給料などに下がることはまず無いです。
30代地方公務員の管理栄養士の年収
参考までに、
- 残業無し
- 役職無し
- 不要なし
- 手当て無し
公務員の管理栄養士8年目の年収は、470万円でした。
合計年収は600万円を超えていました
ちなみに僕は、公務員の仕事をしている時から「株」をしています。
アベノミクス到来時には、1カ月で500万円以上のマイナスも経験しましたが、現在はプラスですね。
公務員を退職した現在→ステップアップ転職
公務員の経験を買ってもらい、現在はしゃべることを仕事とする管理栄養士をしていますが、年収は800万円を超えています。
高収入の管理栄養士とは
- 研究機関の管理栄養士(600万円~800万円)
- 大学教員の管理栄養士(500万円~1,000万円)
- 複数の収入源のある管理栄養士(給料+無限大)
結果的に、僕の公務員経験は「あくまでステップアップ」だったと感じています。
公務員時代は株の投資以外の副業はできませんでしたが、現在は副業OKの業種なのでライターやブログなどのWebでの収入も得ることができて、自由でありがたいです。
公務員の本格的な受験を考えるなら勉強をはじめよう

僕の経験や後輩の経験を交えると、受験者の8割はあまり勉強をせずに受験しています。
「受かれば儲け」「友達が受けるから」こんな理由の人は、まず受かりません。
なぜなら、本気で受験する人はかなり勉強していますよ。
[chat face=”kowaiusagi.png” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none”] でも、どうやって公務員試験の勉強をしたらいいのだろう? [/chat]
と言う人のために、独学で勉強した僕の経験をまとめています。
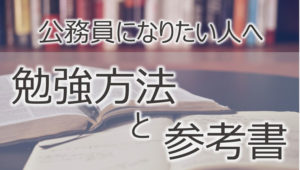
もちろん予備校に通うのも手ですが、僕は田舎者なので予備校もなく、独学で突破しました。
ちなみに、2市1県受験して、全て合格しています。
有給は20日ある
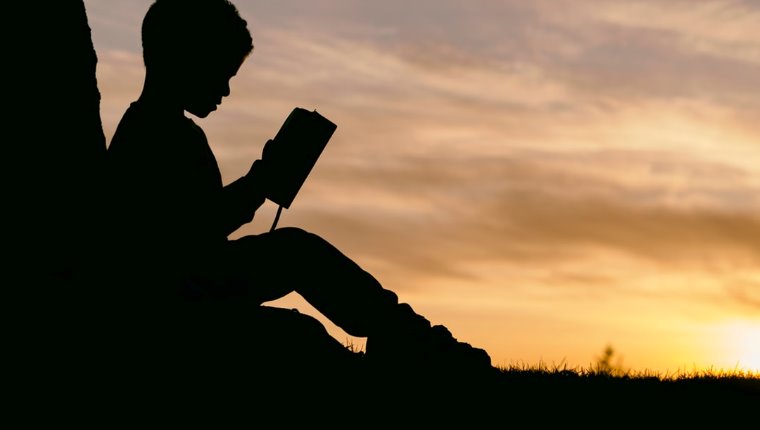
公務員は休んでも給料がもらえる休み【有給】があり、公務員の世界では【年休】と呼びます。
- 年休:20日
- 病院通院休暇:5日
- 夏休み:3日
- 人間ドック休暇、子看休暇、介護休暇、などなど
多くの休みがありますし、休みすぎても文句は言われません。
なぜなら、上司が休みについて発言してしまうとパワハラになるからです。
まとめ

20代、若い時の公務員の年収は業務エネルギーの割に低いです。
しかし、30代になってくれば業務量は落ち着き、仕事はアイデアで裁くようになります。
つまり、低エネルギーである程度の仕事量をこなせるようになるわけです。
その頃には給与も増え、公務員の仕事のメリットを感じるようになりますよ。















